| 今回はとても刺激的な生き方をしている女性が書いた本をご紹介します。 |
|
養老静江著『ひとりでは生きられない〜紫のつゆくさ ある女医の35年〜』、
かまくら春秋社、2004年
|
内容
冬休みなので、今回は趣味の本をご紹介します。
物心ついた頃から、私は潔く生きるプロフェッショナルの女性に憧れをもっていました。自分もそんなふうに生きていきたいと、人生のモデルにしてきたようにも思います。そのためか、女性が主人公のドラマや小説、女性の書いたエッセイが好きで、男性が主人公のものよりもはるかに多く読んでいる気がします。
2013年も、いろいろな女性が書いたエッセイを読みました。上野千鶴子さん、香山リカさん、渡辺美紀さん、林真理子さん、曽野綾子さん、酒井順子さん…。
そんな女性が書いた本のなかから、今回は私の生き方を刺激した3人の本をご紹介します。
まずは、私が最も影響を受けた人である養老静江さんの自伝です。養老静江さんは、言わずと知れた養老孟司さんのお母様であり、小児科医院を開業していた女医で、93歳の時に業績をあげた女医に授与される荻野吟子賞を受賞されています。
この静江さんの生き方が、自由奔放で波乱万丈、大河ドラマにしたいくらいなのです。女学生で女医免許の取得、弁護士と結婚し二人の子の出産したものの離婚、二人の子連れ再婚をして養老孟司さんを出産するが、5年で最愛の夫と死別。その後は、95歳で亡くなるまで現役の小児科医でした。
この本のなかで、若い頃の私の目を開かせてくれた箇所があります。子どもの頃、静江さんは草原に寝ころんで、大空を眺めてこんなことを思います。「私が死んだら、この空も水も人もない。私がいるから私には空も水も人もある。大切なのは、私なんだ。私の心なんだ。そうだ私の心のままに生きて行こう。」(p.25)。
私は20年前に静江さんのこの言葉を新聞記事で読み、その言葉が掲載されていた記事を切り抜き、いつも持ち歩いていました。そして折々に読み返しては、「私も私の心のままに生きていこう」と決意を新たにしたものです。その結果、なんともマイペースな研究者になってしまったのですが。。。
静江さんの生き方は、読む人によっては倫理的な面から賛否両論あるでしょう。でも私にとっては、最後まで自分の心のままに生きた姿が最高にかっこよく映りました。これが明治に生まれた女性であったことにも、また驚きを禁じえませんでした。
目次
まえがきにかえて 母を論じる 養老孟司
第1章 紫のつゆ草―遠い風景
遠い風景
ふるさと
幼い夢
寄宿舎生活
女子医専へ
女医に
東京帝国大学医局
関東大震災
心乱れて
結婚
再び医療へ
美しい眼
ふるさとへ
第2章 紫のつゆ草―新しい旅だち
鎌倉の二階家
小児科大塚医院
鎌倉ぐらし
不治の病
しのびよる影
夫の発病
愛する人との別れ
終戦
業
第3章 ひとりでは生きられない
愛する人へ
新しい時代の主役たち
「いのちの母」の幸せ
「パパ、こめんなさい」
我が家は梁山泊
音痴から始まった
お祭りばあさん
荻野吟子賞をいただいて
ペンペン草の歌
深く沈んだふるさと
ほのかなるもの
一葉の写真
旅の始まり
恋は痛くて苦しいもの
墓参り
あこがれ
反省しきり
あとがき 養老静江
|
    |
草間彌生著『無限の網 草間彌生自伝 』、作品社、2002年
|
内容
これまた超有名な芸術家、草間彌生さんの自伝です。草間さんの作品とは、直島に行った時やその他のいくらかの場面で出会っていましたが、その作品を最も堪能したのは草間さんの故郷である松本市立美術館に行った時でした。ちょうど私が松本市のホテルに缶詰めになり、論文執筆に向けた一人合宿を行っている最中に、気分転換に出掛けたのです。草間さんの作品の展示に加え、様々な本を販売していました。その時に買い、一気に読んだのがこの本です。
タイトルの通り草間さんの自伝で、少女時代から芸術家になり前衛的な作品を次々と発表する過程が描かれています。1970年代に彼女が「スキャンダルの女王」と評されていた所以がわかります。多分、その頃の彼女の感性が時代を追い越していて、時代が彼女を理解し追いついていなかったためなのでしょう。
この本のなかで私が心打たれたのは、彼女の芸術に対する姿勢に対してです。日本で芸術(家)を育てなければならないと彼女は言います。「日本には自国の文化を育てる画商というものが、ほとんど存在しない。…美術館も画商も美術雑誌の人たちも、みんなで自分の文化を振興させようと思って、自分たちの生命を賭けて文明に対するチャレンジをやってほしい」(p.232)。「自分の作った作品が日本という社会の中で、どれだけ人の心を揺さぶることができるのかわからなかった。でも、自分の道を貫くしかない。死ぬまで私の主張をつづけて、この荒廃の中でたとえ悲しい思いをしても、自分の考えを芸術の中に命がけで表していけばいいのだ、と私は思い直した。それで百年後に誰かが私の作品を見て、草間さんはいい仕事をしたと思ってくれれば、それで満足だと思っている。」(pp.233-234)。「人生は真実素晴らしいとつくづく思い、体が震えるほど、芸術の世界は尽きることなく興味があり、私にはこの世界しか希望のわく、生きがいのある場所は他にないのだ。そして、そのためには如何なる苦労をしても悔いはない。私はそのようにこれまで生きてき、これからもそう生きてゆく。」(p.247)。
身を削りながら魅了されたものに専心する、この姿こそが自分が追い求め続けてきた「あこがれ」の正体なのでしょう。
目次
第1部 ニューヨークに渡って―前衛アーティストとしてのデビュー 1957‐1966
第2部 故国を去るまで―画家としての目覚め 1929‐1957
第3部 反戦と平和の女王となって―前衛パフォーマンスの仕掛け人 1967‐1974
第4部 私の出会った人、愛した人―G.オキーフ、J.コーネル、A.ウォーホル他
第5部 日本に帰ってから―日本から発信する世界のクサマ 1975‐2002
|
    |
内容
言葉での表現は難しいのですが、「自分の感性のあり方とどことなく似ているなぁ」と、高校生の時からそう思って音楽を聴いてきたのが大貫妙子さんです。彼女の歌からは「透明な清々しさ」と、「神秘さや不思議さに目をみはるセンス・オブ・ワンダー」、そして、「人の温かさを感じられるほどの孤独と距離感」を感じていました。
そして今回、エッセイ集を読んでみて、上記の三つに加えて大貫さんの「豊潤な暮らしぶり」を感じました。それは決して物質的な豊かさにというわけではなく(もちろん物質的にも豊かなのでしょうが)、「暮らし」に対する細やかさと豊かさと言えばよいのでしょうか。例えば、美味しくないと言われることもある玄米の炊き方に関して、こんな一節があります。「夏には十二時間、冬なら二十四時間くらい浸水させ、私はその水をいったん捨ててから、あらたに炊く。面倒に思えるかもしれないが、「玄米はよく噛んで食べるように」という常識からはほど遠いくらい、ふっくら柔らかで、もちっと炊ける。…玄米は身体の掃除にもなるし、免疫力も上がる。副食の数も少しでいいし、力が出る。だから歌う日は必ずしっかり食べて行く。ちゃんと炊くと白米より絶対においしい。」(p.174)。そしてその後も、どのような火加減で炊くといいのかが述べられています。自分の心身の状態に合わせて調整し、丁寧に暮らす姿が豊かだなと思いました。
そしてまた、私の「あこがれ」る大貫さんの姿勢が綴られているのです。「芸術にはもともと奉納という意味合いがあり、私も長くその思いを忘れず続けてきた。歌は声であり楽器である。それはあるとき、天と地を結ぶものであり、届けるものでもある。人は誰でも歌うことができ、その声と向き合うとき、心が自由になる瞬間を知っていると思う。それを磨いていくことが芸能であるということを、忘れてはならないと思っている。」(p.209)。
この言葉を自分に置きかえてみると、何かを学んで新しい概念や物の見方を身に付けた時に、それまで見えなかったものが見えてきたり、違う世界が広がっていることがあります。そんな時、少しだけ自由になれた気がします。だから学ぶことをやめられないのでしょうね。
この本を読んで、歌だけでなく大貫妙子という人がますます好きになりました。
目次
田植えとおしくらまんじゅう
十八年目のただいま
守宮といつまでも
暗闇のなかの対話
ナマケモノを見に行く
歌う私、歌わない時間
地球は誰のものでもない
二十年ぶりの買い物
楽しいこと嬉しいこと
空蝉の夏
天の川
ぎんちゃん
御蔵島にて
親と歩く
猫の失踪
庭とのつながり
ともに食べる喜び
ツアーの日々
贈りもの
東北の森へ
向こう三軒両隣
お母さん、さようなら
ノラと私のひとりの家
迎えて、送る
高野山で歌う
春を待つ
荷物をおろして
|
    |
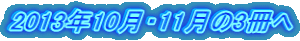
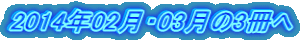
|
|
|
|

