| これまでに印象に残った原作本と映画を見比べてみました。内容がわかってしまう可能性もありますのでご注意を。(2008年3月) |
原作タイトル:「刑務所のリタ・ヘイワース」
『ゴールデンボーイ~恐怖の四季春夏編』(スティーブン・キング,新潮文庫)
映画タイトル:「ショーシャンクの空に」
たいていは原作の方が面白いのですが、この作品は映画の出来が圧倒的に上回っています。これまで何百本の映画を観てきた私にとっての、ベスト1映画でもあります。無実の罪で長期服役中の主人公が、持ち前の知性と持続力を活用し、自由を手に入れるまでのお話です。
原作の主人公が風のなかでズボンのポケットから土をまく部分では、主人公の周りで土ぼこりが舞っているシーンを想像していましたが、映画は静かに地面に土を捨てていくというもの。考えてみたら、目立ってしまうとその土はどこから持ってきたの?となるので、そのシーンが地味なのは当然のことでした。
また、映画では、主人公や登場人物の苦悩がよく描かれており、最後のシーンでは主人公が自由になった開放感が画面一杯から伝わってきました。だから映画ってやめられない!!と実感した作品です。多分、今後もマイベスト映画の地位は揺るがないでしょう。
|
 |
原作タイトル・映画タイトル:『潜水服は蝶の夢を見る』(ジャン・ドミニク・ボービー,講談社』
昨年の暮れに本を読み、まれにみる感動ぶりでした。脳梗塞によるロックトイン症候群になった主人公が、唯一自分の意志で動かすことが出来る左目で20万回まばたきすることにより、書き上げた本です。筆者は元フランスのファッション雑誌『ELLE』の編集長だけあり、文章はウィットに富み、本全体からエレガントさが伝わってきます。電車のなかで原作を読み終えて、その心の強さに感動し、思わず号泣しそうになりました。
映画では、最初は左目しか見えない主人公の目線でカメラが動いていきます。そして、その後主人公の変わりはてた姿が映し出されるのです。終始、声には出せない心の声が聞こえてくる、映画ならではの演出でした。病を持った人はこんなもどかしさ、辛さを感じるのだなということが伝わってきます。
身体は潜水服を着ているようだけど、心は蝶のように過去にも未来にも飛んでいけるという、心の力を教えてくれる作品です。映画の最後に、主人公が肺炎になって亡くなる前に『まだこれからだったのに』という心の声が聞こえたときには、『ああ、無念だろうな』と私も悔しい気持ちになりました・・・。
|
 |
原作タイトル・映画タイトル:『チーム・バチスタの栄光』(海堂尊,宝島社文庫)
難易度の高い心臓のバチスタ手術でホープの桐生医師が、連続して術中死をだしてしまい、その原因究明のために神経内科田口先生が特命を受けるという原作は、楽しんで読めました。元病院に勤めていたこともあり、これまで医療系ミステリー(法医学関係を含む)はかなり好きで、何冊か読むなかでやはり「このミステリーはすごい!大賞」を受賞しただけあり、この本は秀逸だなという感がありました。漫画まで買って読むほど、はまりました。
映画化されると聞きキャストを知ったときに、私のなかでは神経内科の田口先生は当然阿部寛だと思っていました。あのヌボーッとした優しい雰囲気は田口先生にピッタリだと思ったのです。しかし、蓋を開けてみると竹内結子が田口さんで、阿部さんは白鳥さんではありませんか!?白鳥さんはもっと暑苦しくて太っていて、存在感がある「ウザイ」人がやるべきでした。阿部さんのようなスマートな人ではなく・・・。
さらに、バチスタ手術の執刀医桐生医師も吉川晃二ではないよなぁ・・・という感じ。むしろ辰巳琢郎のイメージ。もちろん、阿部さんも竹内さんも吉川さんも演技はそれなりなのですが、やはりキャスティングの問題は大きいです。
今後、違うキャストで作ったら、もっと面白いものになるでしょうね。
|

|
原作タイトル・映画タイトル:『犯人に告ぐ』(雫井脩介,双葉文庫)
原作は面白いのに、映画化するとその醍醐味がそがれてしまう典型例がこの作品でした。幼児連続殺人事件の犯人を公の場にあぶりだすべく、刑事がテレビに出演して犯人に呼びかけることがこの作品タイトルにつながっています。
原作では、主人公の上司の若手キャリア官僚が、主人公が出演していない他局のニュースキャスターの気を引きたいうえに、主人公を出し抜きたいがために、ニュースキャスターに捜査の内部情報をリークします。そして、捜査情報が外部に漏れた原因を探るために主人公らがある仕掛けをすることで、上司の背信を暴露するシーンがあるのです。しかし、そのシーンが映画には全く入っていないころが、醍醐味がそがれた一因でもあると思います。
テレビで公開捜査をするという発想もさることながら、この作品の「肝」は苦悶する主人公の内面を描くことであり、それが不十分であるため映画は原作ほど突き抜けていないのです。
ちなみに上演シアターが、関東では作品の舞台となった神奈川県+アルファでしかなかったことも、何か背景があったのでしょうか・・・。
|
 |
原作タイトル・映画タイトル:『博士の愛した数式』(小川洋子,新潮社)
原作は、さすが第1回本屋大賞と第55回読売文学賞を受賞しただけあります。交通事故による高次脳機能障害で記憶が80分しか持続しなくなってしまった元数学者の「博士」と、博士の家政婦である「私」とその息子「ルート」の心のふれあいを、美しい数式を通して描いていきます。
映画のキャストも、博士にはほどよく渋みが出た寺尾聰、家政婦には健気な演技が光る深津絵里、大人になったルートにはやるせない優しい演技をさせたらピカイチの吉岡秀隆と、はまり役ぞろいでした。
映画では全体を通して、穏やかなトーンのなかに過去の秘められた熱い思いを潜ませてあおり、ジワリとしたインパクトのある作品になっています。原作と映画のギャップがほとんどない作品でもあります。
博士や吉岡君のレクチャーを聞いていたら、数学嫌いな私も思わず数字の美しさに魅せられてしまいました。
|
 |
原作タイトル・映画タイトル:『疾走』(重松清,角川文庫)
残念ながら、これもまた原作の臨場感、主人公の深い絶望感が映画では描ききれなかった作品といえるでしょう。干拓地と水平線が広がる町に暮らす主人公の少年は、兄の犯罪をきっかけに一家離散の憂き目にあいます。少年にとって走ることが唯一の救いですが、自分自身の人生をもかくも早く走り去ってしまうのです。
映画では、主人公の悲惨な状況を手加減して描いているがために、深い絶望感が伝わってこない結果となってしまいました。例えば、主人公が拠り所にしている教会の神父とともに、殺人の罪で服役している神父の弟に会いにいくシーンは、原作では心の奥底に響くような衝撃があるのですが、映画ではインパクトが弱められています。また、原作では主人公が住み込みで働いていた新聞配達店で、同室のおじさんに稼いだお金を盗まれる場面がありますが、それも映画では取り入れられていませんでした。
それでも、主人公を演じた手越祐也君が、一生懸命頑張っていたから許してあげましょう!!
|
 |
原作タイトル・映画タイトル:『嫌われ松子の一生』(山田宗樹,幻冬舎文庫)
この作品は元インテリの松子が人生へのヴィジョンの弱さと男性への依存から、紆余曲折しながら転落していく姿を描いたものです。原作は『どうしてそこでそうするかなっ』と、心のなかでブツブツ叫びながら一気に読んでしまいました。でも、なぜか松子は憎めません。
映画では、中谷美紀が松子を演じており、ミュージカル仕立ての軽快な仕上がりになっています。ただ、あまりに軽快すぎて、濃淡に乏しくジェットコースターのような筋書きをなぞるだけの感が否めないのが残念です。
特にこの作品の「最後の砦」といえるのは、運命の人龍洋一が服役明けで松子の元に戻ってくるにも関わらず、あまりに松子の愛情がまぶしくて逃げ出してしまう場面です。そこで、松子の心の糸がプツリと切れるため、そこを最大の見せ場にするべく演出が必要でした。
それでも、最後に松子が天に召される時に、暖かい家族が待っている自宅の階段を昇っていくシーンでは、涙ぐまずにはいられませんでした。
|

|
原作タイトル・映画タイトル:『ダ・ヴィンチ・コード』(ダン・ブラウン,角川文庫)
言わずと知れた、全世界のベストセラーです。ルーブル美術館館長の死の謎を解くため、宗教象徴学者の主人公が奔走する話です。キリスト教の暗喩がところどころにちりばめられていて、初めて触れる世界でしたが新鮮な発見に満ちていました。これからはダ・ヴィンチの絵を、違う角度から観ることができそうです。
映画では、アカデミー賞俳優のトム・ハンクスが、達者な演技力で主人公を演じていました。原作のボリュームが大きい上に、これまたジェットコースターストーリーのため、映画の枠に閉じ込めてしまうにはいささか無理はありましたが、最後はなんとか帳尻を合わせてくれたかんじです。原作に忠実な点には好感が持てました。
それにしても、ヒロインのオドレイ・トトゥのキュートなこと。女の私でも惚れそうです。
|
 |
原作タイトル・映画タイトル:『陰日向に咲く』(劇団ひとり,幻冬舎)
一昨年の夏、調査旅行に出たときに、共同研究者に面白いからと薦められ、電車のなかで一気に読みました。確かに面白く、そして泣かせるストーリー展開で、いくつかの話のオムニバスでありながら、全部どこかで繋がっていて不思議な調和感のある1冊だと思いました。
そして映画化された時、期待を胸に観に行ったものの『なんだ、この水で薄めたようなテイストは』と、半ばガッカリしました。映画の最後には泣かせるシーンが準備してあるのですが、急にその部分の濃度が濃くなるため、まるで今まで水のようなジュースを飲んでいたのにコップの下に原液が溜まっていたという感じなのです。
やはり原作の醍醐味を生かすには、全体的に間延びを防ぎ、各お話の関連性をもう少しわかりやすくして、均一な濃度で上質な飲み物に仕上げてほしいところでした。
主人公のキャラクター設定に対し、演じた岡田君(V6)が高貴でオーラを放ちすぎているのも、チグハグ感が否めない一因かもしれません。
|
 |
原作タイトル:『甲賀忍法帖』(山田風太郎,角川文庫)
映画タイトル:『忍 SHINOBI』
徳川家のお家騒動の代理戦争をするため、先祖代々の宿敵である甲賀忍者と伊賀忍者の精鋭10人ずつが選ばれデスマッチを繰り広げるというもの。しかし、すでに宿敵のはずの両陣営の若き2人の忍は、恋仲でもあったのです。まさに、江戸時代版ロミオとジュリエットといったところでしょうか。
オダギリジョーと仲間由紀恵という美しい2人の悲恋を映画で観て、のめりこみました。原作を読み、漫画を読み、アニメのDVDまで買ってしまい・・・。
でも、原作は映画ほど美しくはないんです。もっとオドロオドロしい特殊能力をもった忍者が次から次へ登場し、その奇想天外ぶりがちよっと痛い。
ウルトラマンの世界を純粋に崇拝していた子どもの頃なら、もう少し長くその世界に浸っていられたのでしょうが、結局、通信販売で買ったDVDは一度も観ることなく不燃ゴミと化しました。
|
 |
原作タイトル・映画タイトル:『ジョゼと虎と魚たち』(田辺聖子,角川文庫)
共同研究者の薦めでDVDを借り、途中からあまりのせつなさに号泣した覚えがあります。ジョゼは足が不自由な女性で、いつも家の中でおばあさんがゴミ捨て場から拾ってきた本を読んで生活しています。ある日、大学生の主人公と出会うことで、まるで深海からさんご礁の海へ泳ぎ着いた魚のように、生活が変わります。映画では、なにより池脇千鶴のヌードも辞さない体当たりの演技と女優魂に感服しました。
ところがその後、原作を読んでみたところ、全くといっていいほど違うお話ではありませんか。共通点はジョゼが足が不自由な女性だということのみ。原作は短編でハッピーエンドなのですが、映画は…。同じタイトルで2つの作品があるといったかんじです。
共同研究者は、この映画を障害をもつ人の生活や恋愛を考えるうえでの、教材にしていると言っていました。私にとっては、人生の教材になっています。
|
 |
原作タイトル・映画タイトル:『電車男』(中野独人,Shinchosha Pablishing)
原作も、映画も、テレビドラマも、けっこう気に入りました。原作は当時のインターネットの掲示板をそのまま再現してあり、この逐語録(?)はテンポよく臨場感にあふれ、読む側を飽きさせません。
映画では、山田孝之演じる「電車男」と中谷美紀演じる「エルメス」が、たどたどしくも距離を近づけていく過程が描かれており、インターネットという最も速効的なツールを使いながらも、もっとも原初的な人と人とのふれあいのあり方を浮き彫りにしている面白い一本でした。果たして『電車男』は実在したのでしょうか?
それにしても、山田君は次に書いた『手紙』の主人公を、中谷さんは「嫌われ松子」という、全く異なるキャラクターを見事に演じきっています。こんな若手俳優が活躍する限り、まだまだ日本の映画界の未来は明るいと、密かに拍手を送るのでした。
|
 |
原作タイトル・映画タイトル:『手紙』(東野圭吾,毎日新聞社)
殺人を犯して服役中の兄と、「犯罪者の家族」として世間の荒波のなかで生きざるをえない弟との間をつなぐのは、たまに書く手紙のやり取りだけ。そんな2人の関係性を軸に、話は時系列で進んでいきます。ある重大な転機を迎えるまでは…。
原作に負けず劣らず、映画もなかなかの出来栄えでした。
ただ一つ、原作と映画との大きな違いがあるとすれば、最後のシーンで弟が兄に自分の心情を伝える手段として、原作では音楽を、映画では漫才を使っていることです。きっと、映画では歌ではなく、弟にダイレクトに兄への気持ちを言わせたかったのでしょう。
エンディングに流れる小田和正の『言葉にできない』が、満開の桜のシーンと溶け合って、せつない決断と未来だけを志向した再出発の機運を盛り上げていました。
|
 |
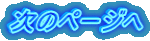
 |
|
|

