|
この書評は立正大学社会福祉学部ニュース『HITA』第19号(平成18年度2期号)に掲載されたものです。
|
<東野圭吾『手紙』毎日新聞社、2003年>
「犯罪者の家族はどこまで罪を背負うのか」が、この本の主題です。この本の主人公は2人います。一人は、弟の大学進学費用を手に入れるため、裕福な老婦人宅に強盗に押し入り殺害し、服役中の兄。もう一人は、唯一の身内とそのような形で離れて暮らし、とにかく生きていかなければならない高校生の弟です。二人の接点は、月一度許される刑務所の兄からの手紙と、それに対する弟の返信の手紙でした。
兄の刑務所での生活は、毎日規則正しい日課のなかで作業を行うことであり、たまに来る身内からの手紙が唯一の楽しみです。一方、弟の生活は波乱に満ちています。といっても、遭遇する出来事のほとんどは、辛さ、悲しみ、苦しみに彩られています。アルバイトを見つけても、好きな女性ができても、ボーカルであるバンドのデビュー話があっても、ことごとく破綻してしまうのです。これは、全て「犯罪者の弟だから」という理由でした。
物語が終盤に近づく頃に、弟は「世間」の象徴かつ代弁者である一方で、新しい扉があることを教えてくれるキーパーソンと出会います。それが、正社員として働いている会社の社長なのです。ふとしたきっかけで兄のことが明るみに出て、社内での配置転換を言い渡されます。その時に目の前に現れた社長は、弟にこう言うのです。「差別はね、当然なんだよ」「犯罪者やそれに近い人間を排除するというのは、しごくまっとうな行為なんだ」「人には繋がりがある。愛だったり、友情だったりするわけだ。それを無断で断ち切ることなど誰もしてはならない。だから殺人は絶対にしてはならないのだ」「君のお兄さんはいわば自殺をしたようなものだよ。社会的な死を選んだわけだ。しかしそれによって残された君がどんなに苦しむかを考えなかった。衝動的では済まされない。君が今受けている受難もひっくるめて、君のお兄さんが犯した罪の刑なんだ」。そして弟は、この社長との関わりを機にある決断をするのですが、それはここでは書かないことにしておきましょう。
さて、私はこの物語を読み終えた時に、複雑な気持ちになりました。まず、犯罪者の身内が引き受けなければならない罰とは、かくも深いものなのかと思ったのです。犯罪者の身内だったら救いはないのか、との疑問も持ちました。そして、世間における差別や偏見の根強さも感じました。結局、一度レッテルを貼られたら完全に払拭しないかぎり、どこかで差別や偏見の種火はくすぶっているということを本のなかでは伝えています。そしてそれは、親から子へと受け継がれていき、差別と偏見の連鎖は連綿と続いていってしまうのです。これはかなり重大な問題でもあります。この解決策はまだ自分では見出せてはいませんが、これから考えていくべき大きな課題であることを、本書を通して痛感しました。
東野圭吾氏は、直木賞他数々の受賞歴のあるミステリー作家です。『白夜行』や『秘密』など、これまでに多くの作品が映画やドラマ化されています。この『手紙』も秋には映画になったため、ご覧になった人も多いのではないでしょうか。数ある作品のなかでは、際立って社会的な視点が強いこの作品を、ぜひ一読されることをお勧めします。
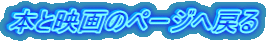
|
|
|

