| 旅の締めくくりに、今の私にとってスウェーデンがどんな国かを綴っておきましょう。 |
旅の準備は、いつも1年前から行います。日本でのコーディネーターである旅行のプロ小野鎮さんと、スウェーデンでのコーディネーター兼通訳であるスティアー純子さんにメールを出し、コーディネートを依頼します。視察のテーマ、希望の場所、日時、人数、参加者等について、何度かにわたるメールのやり取りのなかで固めていきます。常に的確な2人のリードで、毎回、快適な旅が実現できています。
学生と行った時にはペンションを、教員仲間と行った時にはホテルを確保してもらいました。でも、常に変わらないのは、いつも参加者の役割を決めること、一定の金額を集めて共通経費とし、視察先へのお土産を皆で持っていくこと、そして「食事」のページで紹介したように最後の夜にはグランドホテルでスモーガス・ボードのディナー・パーティーを行うことです。
4回とも冬に行ったので、いつも荷物はスーツケース一杯になり、ダウンジャケットやカイロ、厚手の靴下とブーツといった防寒具は万全に備えます。一度、マイナス15℃という顔まで凍りつきそうな寒さの日がありました。でも、建物の中はとても暖かかったです。それでも、毎回風邪をひいてしまう私でした。
|
 |
一番最初に行った時は、素晴らしい点しか見えませんでした。でも、徐々に影の部分も見えてきました。
まず目につくのは、町の汚さです。ゴミやタバコの吸殻が道端に散乱していることに、落胆しました。純子さんによれば、予算が町の美化までまわされなかったり、除雪した雪をそのまま川に投げ込むため、川が汚染されたりするとのことでした。
やはり、予算という現実のパイの問題はどこにでもあり、スウェーデンとて決してお金は無尽蔵ではないことを感じさせられました。
また、日本では「福祉先進国」のイメージがありますが、やはり内部ではまだまだ障がいをもった人への偏見があったり、バリアがあるのも現実のようです。
前に書いたように、ドメスティック・バイオレンスも、やはり後を絶ちません。
同じ人間が住んでいる地球上どこでも、哀しい「人間の性」は変わらないのかもしれません…。
|
 |
それでも、やはり何度もスウェーデンに行きたくなる魅力の一つは、スティアー純子さんに会えるためです。
純子さんは日本で看護師をしていた時に、交換留学生としてスウェーデンに渡りました。そしてスウェーデン人の連れ合いと結婚し、子どもが生まれ、もう何十年もスウェーデンに住んでいらっしゃいます。
とてもプロ意識が高い方で、いつも強力なサポートをしてくださり、安心感と満足感を提供してくれます。
一度、視察先で満足のいく視察が出来なかった時に、純子さんは自宅に私たち全員を招いて、ワッフルをご馳走してくださいました。海に面した豪邸で、私たちは一時、ゴージャスな気分に浸ったものです。
写真は、最後の夜の晩餐会で、純子さんがスウェーデンの連れ合いの親からプレゼントされた緑色のドレスを着てくださった時のものです。私たちの晩餐に、美しく着飾ってくださったことが、とても嬉しかったです。
|
 |
3回目の旅行で、私はそれまでにない2つの感覚に囚われました。
一つはホームシックです。自由時間に一人でストックホルムの町を歩いた時、目指すべき図書館に辿り着けずに、夕暮れの町をウロウロと歩きまわりました。その時、なんとも寂しく、何かから取り残されているような気持ちになったのです。きっと日本では、私の知らないニュースが起こり、年度末の慌ただしさのなかで人々は働いているのだなと思いました。
その時の旅行は、私の一つの節目になる「卒業旅行」であり、たまにはパソコンも電話もない暮らしに浸る喜びを感じるのも良いと思っていたのですが、そのような状態に心身を委ねられない自分に、とても戸惑いました。写真は、道に迷った時に高台からストックホルムの町を写したものです。
そしてもう一つは、「自分が以前より歳をとった」という感覚です。その時は、それまでの旅行と違うことが多々ありました。いつもより日本食が恋しいこと、行きも帰りも時差ぼけの解消が遅いこと、いつもよりヨーロッパが遠く感じられたこと…。私はこの時「老いの途上にある自分」に気づいたのです。
「老い」は、ある日突如として訪れるのではありません。春の日に夏の兆しがあるように、夏の日に秋の気配が潜んでいるように、30代の時も、40代の時も、老いの途上にあるのです。そして、たまにそれに気づくことがあり、私の場合はスウェーデンという異国の旅を通してでした。
人生という長い旅の途上に、短期間、異国に旅をするという「入れ子」構造の際に、それまでの日常では見えないものが強烈に凝縮されて見えてきました。それが、日本への愛着心と移り行く自分の「生」だったのです。そしてそれ以来、私の人生は次の季節に移行しました。
今は、これまでには見えなかった影の部分や、この先自分に残された時間が有限であることがわかってきました。そんな自分がまた次にスウェーデンに行った時には、新たな景色に出会えることでしょう。
いつかまた訪れます、「ほんの隣の国」へ。
|
 |
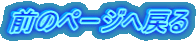
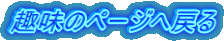
|
|
|

